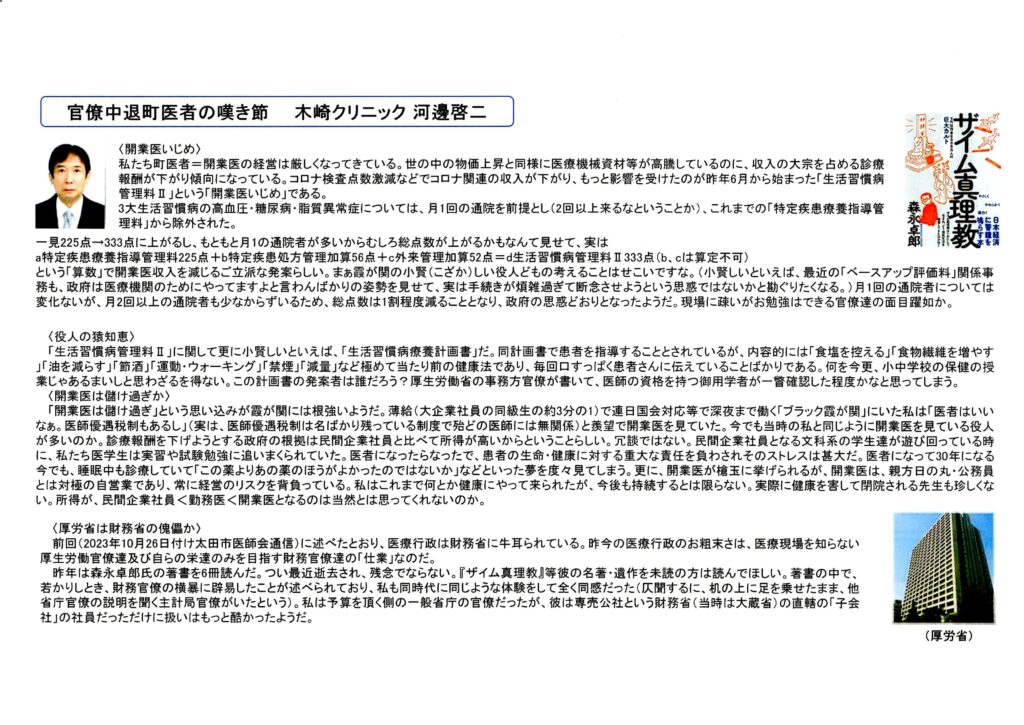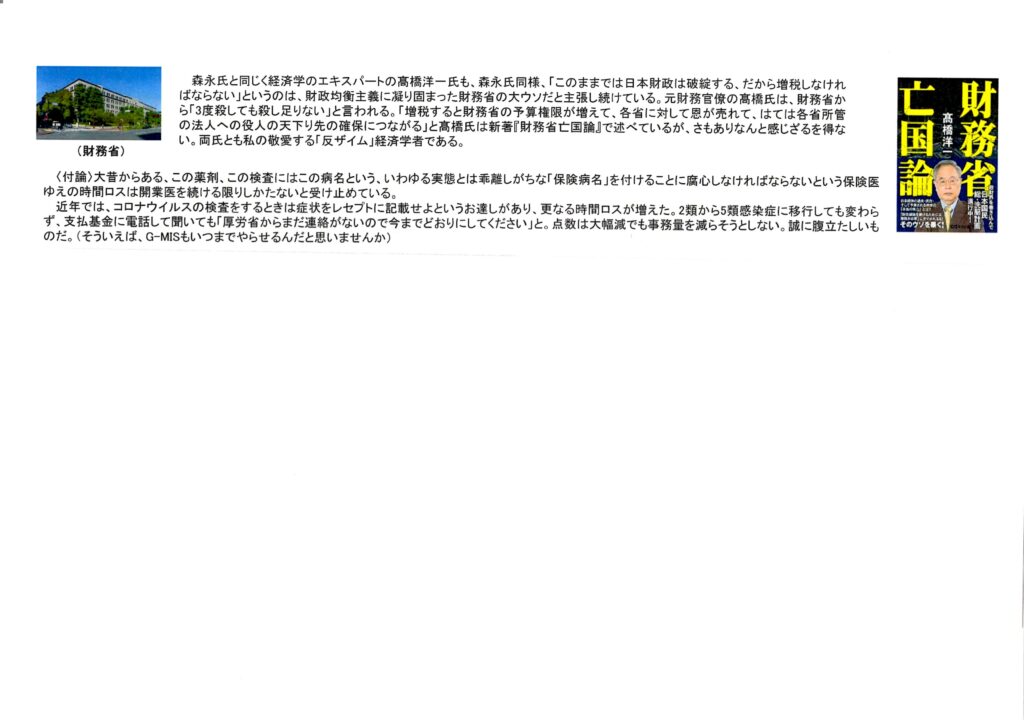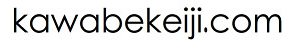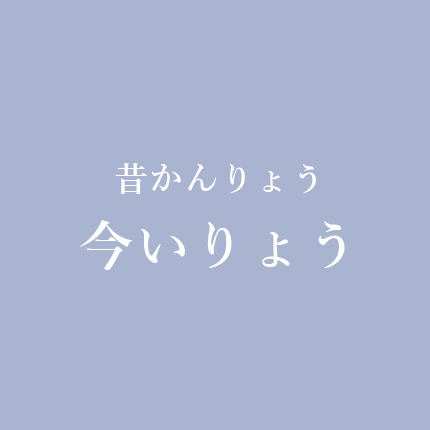太田市医師会通信で私見をー第2弾―
・・・・・・・・・・・・・河辺啓二の医療論(39)
2023年に続き、再度、太田市医師会通信で私見を述べる機会をいただいた。引き続き、医療行政批判などを述べてみた。
なお、前回のものは⬇のとおり。
太田市医師会通信で私見を | 河辺啓二 kawabekeiji.com
太田市医師会通信(第59号 2025年2月27日)から当該箇所のみをここに載せることとする。
やはり現物は文字がやや小さくて読みにくそうなので原案を先に示す。
官僚中退町医者の嘆き節 木崎クリニック 河邊啓二
〈開業医いじめ〉
私たち町医者=開業医の経営は厳しくなってきている。世の中の物価上昇と同様に医療機械資材等が高騰しているのに、収入の大宗を占める診療報酬が下がり傾向になっている。コロナ検査点数激減などでコロナ関連の収入が下がり、もっと影響を受けたのが昨年6月から始まった「生活習慣病管理料Ⅱ」という「開業医いじめ」である。
3大生活習慣病の高血圧・糖尿病・脂質異常症については、月1回の通院を前提とし(2回以上来るなということか)、これまでの「特定疾患療養指導管理料」から除外された。
一見225点→333点に上がるし、もともと月1の通院者が多いからむしろ総点数が上がるかもなんて見せて、実は
a特定疾患療養指導管理料225点+b特定疾患処方管理加算56点+c外来管理加算52点
=d生活習慣病管理料Ⅱ333点(b、cは算定不可)
という「算数」で開業医収入を減じるご立派な発案らしい。まぁ霞が関の小賢(こざか)しい役人どもの考えることはせこいですな。(小賢しいといえば、最近の「ベースアップ評価料」関係事務も、政府は医療機関のためにやってますよと言わんばかりの姿勢を見せて、実は手続きが煩雑過ぎて断念させようという思惑ではないかと勘ぐりたくなる。)月1回の通院者については変化ないが、月2回以上の通院者も少なからずいるため、総点数は1割程度減ることとなり、政府の思惑どおりとなったようだ。現場に疎いがお勉強はできる官僚達の面目躍如か。
〈役人の猿知恵〉
「生活習慣病管理料Ⅱ」に関して更に小賢しいといえば、「生活習慣病療養計画書」だ。同計画書で患者を指導することとされているが、内容的には「食塩を控える」「食物繊維を増やす」「油を減らす」「節酒」「運動・ウォーキング」「禁煙」「減量」など極めて当たり前の健康法であり、毎回口すっぱく患者さんに伝えていることばかりである。何を今更、小中学校の保健の授業じゃあるまいしと思わざるを得ない。この計画書の発案者は誰だろう?厚生労働省の事務方官僚が書いて、医師の資格を持つ御用学者が一瞥確認した程度かなと思ってしまう。
〈開業医は儲け過ぎか〉
「開業医は儲け過ぎ」という思い込みが霞が関には根強いようだ。薄給(大企業社員の同級生の約3分の1)で連日国会対応等で深夜まで働く「ブラック霞が関」にいた私は「医者はいいなぁ。医師優遇税制もあるし」(実は、医師優遇税制は名ばかり残っている制度で殆どの医師には無関係)と羨望で開業医を見ていた。今でも当時の私と同じように開業医を見ている役人が多いのか。診療報酬を下げようとする政府の根拠は民間企業社員と比べて所得が高いからということらしい。冗談ではない。民間企業社員となる文科系の学生達が遊び回っている時に、私たち医学生は実習や試験勉強に追いまくられていた。医者になったらなったで、患者の生命・健康に対する重大な責任を負わされそのストレスは甚大だ。医者になって30年になる今でも、睡眠中も診療していて「この薬よりあの薬のほうがよかったのではないか」などといった夢を度々見てしまう。更に、開業医が槍玉に挙げられるが、開業医は、親方日の丸・公務員とは対極の自営業であり、常に経営のリスクを背負っている。私はこれまで何とか健康にやって来られたが、今後も持続するとは限らない。実際に健康を害して閉院される先生も珍しくない。所得が、民間企業社員<勤務医<開業医となるのは当然とは思ってくれないのか。
〈厚労省は財務省の傀儡か〉
前回(2023年10月26日付け太田市医師会通信)に述べたとおり、医療行政は財務省に牛耳られている。昨今の医療行政のお粗末さは、医療現場を知らない厚生労働官僚達及び自らの栄達のみを目指す財務官僚達の「仕業」なのだ。
昨年は森永卓郎氏の著書を6冊読んだ。つい最近逝去され、残念でならない。『ザイム真理教』等彼の名著・遺作を未読の方は読んでほしい。著書の中で、若かりしとき、財務官僚の横暴に辟易したことが述べられており、私も同時代に同じような体験をして全く同感だった(仄聞するに、机の上に足を乗せたまま、他省庁官僚の説明を聞く主計局官僚がいたという)。私は予算を頂く側の一般省庁の官僚だったが、彼は専売公社という財務省(当時は大蔵省)の直轄の「子会社」の社員だっただけに扱いはもっと酷かったようだ。
森永氏と同じく経済学のエキスパートの髙橋洋一氏も、森永氏同様、「このままでは日本財政は破綻する、だから増税しなければならない」というのは、財政均衡主義に凝り固まった財務省の大ウソだと主張し続けている。元財務官僚の髙橋氏は、財務省から「3度殺しても殺し足りない」と言われる。「増税すると財務省の予算権限が増えて、各省に対して恩が売れて、はては各省所管の法人への役人の天下り先の確保につながる」と髙橋氏は新著『財務省亡国論』で述べているが、さもありなんと感じざるを得ない。両氏とも私の敬愛する「反ザイム」経済学者である。
〈付論〉
大昔からある、この薬剤、この検査にはこの病名という、いわゆる実態とは乖離しがちな「保険病名」を付けることに腐心しなければならないという保険医ゆえの時間ロスは開業医を続ける限りしかたないと受け止めている。
近年では、コロナウイルスの検査をするときは症状をレセプトに記載せよというお達しがあり、更なる時間ロスが増えた。2類から5類感染症に移行しても変わらず、支払基金に電話して聞いても「厚労省からまだ連絡がないので今までどおりにしてください」と。点数は大幅減でも事務量を減らそうとしない。誠に腹立たしいものだ。(そういえば、G-MISもいつまでやらせるんだと思いませんか)