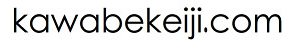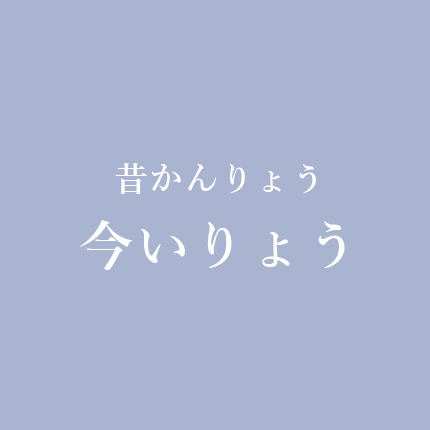コメ政策に疎い元農水官僚
・・・・・・・・・・・・・河辺啓二の政治・行政論(43)

〈メディアに農水省〉
「令和の米騒動」と言われ、かなり時間が経った。マスメディアに農林水産省が頻繁に取り上げられる。こんなに話題になったことあったかなぁなどと思う。私が農水省で働いていた頃、最もメディアに登場するのは当時の通産省(今の経済産業省)だったと思う。私が憧れるも採用してもらえなかった役所だ。(2024年7月21日付け河辺啓二回顧録(Ⅳ):職業選択編②官庁訪問奮闘記 | 河辺啓二 kawabekeiji.com参照)

〈古巣・農水省〉
農林水産省は、約10年間私が所属していた役所だ。懐かしいという感情もある。農水省といえば、農水産物=食べ物というイメージだが、私は食べ物に関した仕事をあまりしていない。元農水官僚と言うことにやや忸怩たるものがないわけではない。振り出しが森林・林業政策の総元締めの林野庁林政部林政課だった。キノコ類は特用林産物で林野庁所管物資であるから、私もわずかながら食べ物に関する仕事を当時したことになる。次の職場は、農産園芸局繭糸(けんし)課だったので、食べ物とは無関係。かつて日本産業を支えた生糸に関する行政だ。その次は、農林水産技術会議事務局で、筑波などに多数ある国立の農林水産関係試験研究機関の元締めの部署だった。だから、食べ物である農産物の研究と多少なりとも接していたことになるが・・・。その後は、当時の総務庁人事局に出向し、官僚人生に終止符を打ったのである。

〈官僚時代唯一の「コメ業務」?〉
というわけで、私は、食べ物にほとんど無関係な農水官僚だったようだが、「コメ」に関した仕事がゼロでもないという記憶がある。
私が役人だった、1980年代には米価審議会(農林水産省の諮問機関。1949年~2001年)があって、そこで農家から政府が買い入れる政府買入価格(生産者米価)と政府が卸売に売り渡す政府売渡価格(消費者米価)を審議して決められていたのだ。その米価審議会の事務局は、当然農水省の役人たちが行うのだが、何課にいたときだったか忘れたが、コメ関係の仕事しているわけでもない私に応援要請があった。何しろ米価審議会、略して「べいしん」は年に1度のお祭り的な行事となっていて、会場前の広場には多数の農業団体が集まってワイワイ騒ぎだった。「農林大臣は、百姓のことだけを考えろ!!」などと叫んでいる人もいた。下っ端役人の私はというと、審議会の状況を記録して素早く本省のお偉方に通告する役割だったと思う。我ながらこういう仕事は向いているようで、レポートを一読した上司から「よくできてる」と褒めてもらった記憶がある。
1990年代以降、医学生→医師となった私にとって、コメの値段―米価なんて全く関心のない事項であった。コメの流通自由化が進んで米価審議会の役割が形骸化し、遂に2001年に「べいしん」は廃止されたそうだが、コメに無関心で医業にいそしんでいた私は、そのことを全く知らなかった(大きいニュースにもならなかったのかなぁ)。

〈進次郎大臣に期待〉
前農水大臣の不適切発言で窮地に至った石破さんが新農水大臣に充てたのがかつて総裁選で争った小泉進次郎氏だ。今のところ「コメ大臣」の面目躍如たるものが感じられる。父親譲りの天性の政治家資質を遺憾なく発揮しているようだ。若くて男前、人気者政治家であることは間違いなく、大きな失策やスキャンダルがなければ、いずれ自民党総裁=内閣総理大臣にまで上り詰める可能性は高いだろう。ただ、その前に、是非財務大臣を経験して一暴れしてもらいたい。閣僚経験を高めるのみならず、霞が関で「最強」かつ「最悪」の役所・財務省を清浄してほしいのだが。

〈ブレる農林水産行政〉
私が官僚の頃はとにかく減反―ゲンタン、ゲンタンだったコメ政策(2018年に減反政策は廃止されたが、補助金による転作誘導は継続していた)が、今や増産に方針変更となって、多くの米農家は困惑している。農林水産行政は、昔から現場を知らない官僚と政治家(他の行政もそうだけど)に振り回され続けているのだ。
第一次産業=農林水産業は、私たちが生きていく上で不可欠な食糧を与えてくれる産業であり、防衛と並んで国家安全保障を担うものである。しかも、天候など自然に非常に影響されるものだから国家として保護育成しなければならないはずだ。
2001年の中央省庁再編統合で、総務省や国土交通省など巨大官庁が出現したため、霞が関における農林水産省の相対的地位は下落したが、今回のことでやや「復権」したのではないか。