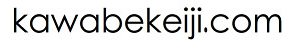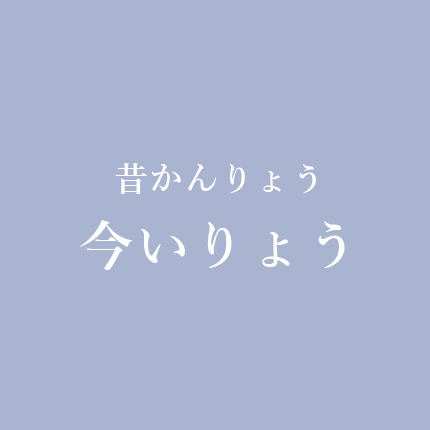戦後80年に読むべき本(近現代史がおもしろい)
・・・・・・・・・・・・・河辺啓二の勉強論(26)
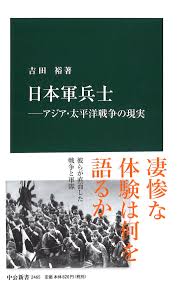
〈8月に読むべき本〉
また、8月が来た。今年は昭和100年、戦後80年である。
まさにこの時期に読むべき名著3冊に出会った。
「日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実」(吉田裕著)2017年12月初版
「続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実」(吉田裕著)2025年1月初版
「日ソ戦争―帝国日本最後の戦い」(麻田雅文著)2024年4月初版
近現代史っておもしろい、興味深いとますます思うこの頃である。テレビでは、大好きな関口宏日本史番組「一番新しい近現代史」(BS-TBS)が毎週土曜に放映されており、私の週末のささやかな楽しみとなっている。今のところ、まだ大正時代―第一次世界大戦の頃を辿っているが。
(週初めは月曜夜のNHK「バタフライエフェクト」が楽しみ)
さて、上述の名著3冊だが、学校で習った歴史がいかに表面的であったかがよくわかる。
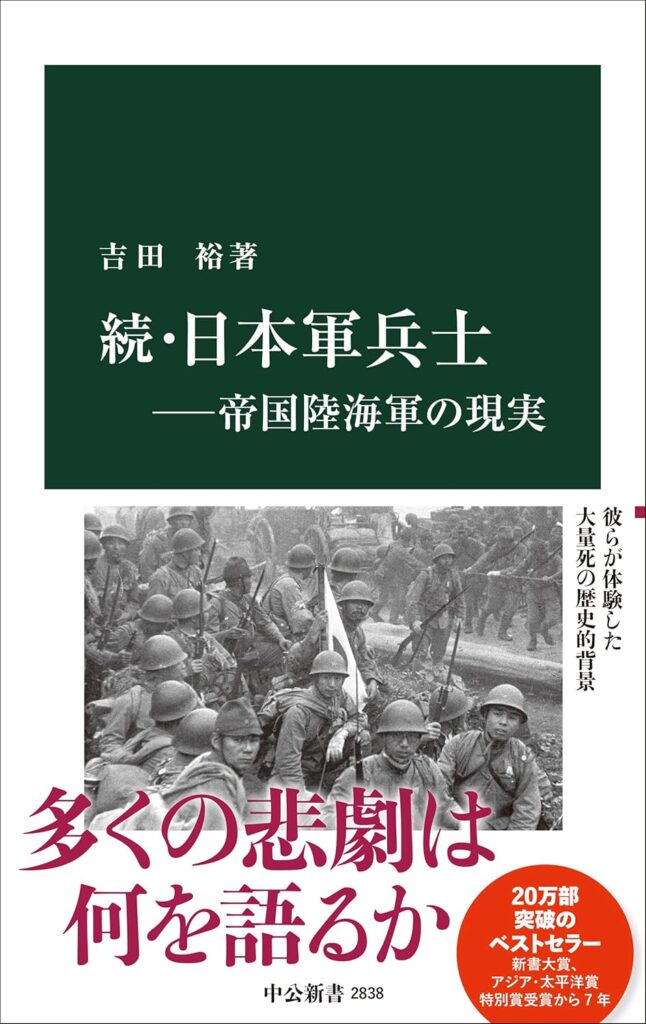
〈あまりにひどい兵士の「労働環境」〉
まず、「日本軍兵士」「続・日本軍兵士」を読むと、いかに日本軍兵士たちが劣悪な環境、特に激烈な不衛生環境に追いやられていたかが詳細に知らされる。医師の私から見て当時の日本軍のお偉方たちの非人間的指示命令には呆(あき)れや怒りを感じざるを得ない。アジア・太平洋戦争で、日本は230万人もの軍人・軍属(軍人でなく軍に所属する文官・文官待遇者等のこと)が犠牲となったが、その6割は戦闘死でなく戦病死だという。栄養失調による餓死者に加え、マラニア等の感染症(栄養失調に伴う免疫力低下が主因)による死亡、更には精神疾患が高じての自殺など、軍からヒトをヒトと思わない扱いを受け可惜(あたら)若い命が失われたのだ。
印象的な記述としては、軍歯科医将校に関するくだりだ。「軍医」はよく知られているが、遅ればせながら歯科医師免許状所有者が歯科医将校となった(しかし、軍医将校とは区別され、軍内部における地位は低かったらしい)。戦場で歯磨きする余裕がなく虫歯・歯槽膿漏の兵士が7~8割もいたという。歯科治療は日本軍の戦地医療で最もおろそかにされていたようだ。歯痛抱えて戦闘せよと言われる兵士たちが気の毒としか言えない。
以前、何かのテレビ番組で観たシーンが思い出される。アメリカの兵士たちは戦闘に行く船中で分厚いステーキをたらふく食べて体力増強しているが、日本兵はやっと握り飯のみで腹を満たしていた。現代の健康オタクからみれば、アブラたっぷりのステーキよりおにぎりのほうが「健康的」かもしれないが、これから戦闘に向かう際に分厚いステーキとおにぎりでは「馬力」の湧き方が違うだろう。しかも、次第に補給が細くなりその握り飯もろくに食えなくなっていた日本軍兵士たちの悲惨さは想像に難くない。

〈8月15日で戦争は終わっていなかったー日ソ戦争〉
我々日本人は、一般的に1945年8月15日が終戦と思っているが、国際的には、同年9月2日、日本政府がポツダム宣言の履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した日が終戦とされている。
しかし、8月8日から9月上旬まで、満州・朝鮮半島・南樺太・千島列島で「日ソ戦争」の死闘が、両軍合わせて200万以上の兵士によって繰り広げられていたのだ。今までも、ソ連の中立条約破棄、ソ連兵士たちの非人道的行いは断片的には知らされていたが、今回の麻田氏の著書「日ソ戦争」(「一番新しい近現代史」出演の小泉悠東大准教授も絶賛)では、夥しい新史料を駆使し、米国のソ連への参戦要請から各地での戦闘の実態、終戦までの全貌が見事に描かれている。
日本人から貴金属、腕時計、万年筆等の強奪、日本人女性に対する性暴力などソ連兵士たちの「蛮行」には反吐(へど)が出そうだ(森繁久彌、宝田明、赤塚不二夫、五木寛之といった著名人の受けた被害がリアルに述べられている)。しかも、スターリンなど指導者たちはこれら「蛮行」を明らかに黙認していたという。
40年前に敗れた日露戦争のリベンジを果たしたなどというロシア側の言い分もあったそうだが、一方的な考えだ。日露戦争後日本で捕虜になったロシア兵士が四国の松山などで親切に扱われた、だから彼らは日本に悪感情を持たなかったという話を聞いたことがある。確かに愛媛の人情味あふれる土地柄ではロシア人を排斥しなかったのだろう。なのに、第二次世界大戦後、日本の一部(北海道)を占領したかったがアメリカに阻まれ、その代わりか、あの「シベリア抑留」があった。57万人とも61万人とも言われる人々が抑留され、6万人も亡くなったというが、正確な数字は明らかでない。
このような極めて非人道的(戦争そのものが非人道的であるが)なソ連、そして「日ソ戦争」を演出した当時のアメリカ(日本を無条件降伏させるためにソ連の対日参戦を熱望。更には原爆投下)はひどい国家だなぁと思いながら、中立条約を結んでいるからとソ連を疑わず、のほほんと米英との講和の仲介役をソ連に頼み続けていた当時の日本首脳の馬鹿さ加減には呆れるばかりだ。
この名著「日ソ戦争」を読むことで、現代の日露関係(北方領土問題など)やウクライナ侵攻に至る「ロシア」という国家・国民の文化・精神の構造がいくらかわかったような気がする。
〈ちなみに〉
同書に「河辺虎四郎」という日本の陸軍軍人がたびたび登場する。役職は大本営陸軍部参謀次長というからエラい軍人だ。歴史に登場する人物に私の名字と同じ人ってほかにいたかなぁ・・・。